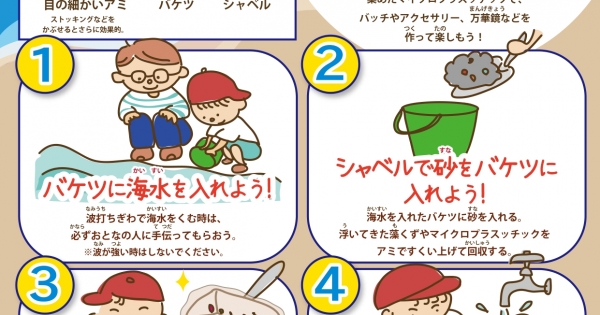Global Wave Conference 2020
2年に一度、世界各地のサーフタウンで開催される『グローバル・ウェーブ・カンファレンス(以下 GWC)』、すなわち国際海洋環境カンファレンス。2020年度はパンデミック化する直前、オーストラリア・ゴールドコーストでの開催だった。GWSとしては第6回目、国際環境NGOサーフライダー・ファウンデーション・ジャパン(以下SFJ)としては3回目の参加となる。

世界中から海に携わる学識者、団体、環境活動家、著名人が集結し、3日間にわたってサザンクロス大学にてカンファレンスが催され、情報共有とコミュニケーションが図られた。各国の海岸地域におけるマイクロ・プラスチック対策や下水処理システム、環境保全や美化、海の自然を活用した地域創生、教育活動など、さまざまな観点で議論された。


僕たちはシェアし、助け合わなければいけない
最初の登壇者はトム・キャロルとニック・キャロルだった。キャロル兄弟は、ゴールドコーストという世界屈指のサーフタウンが 年々混雑していく現状と、ツーリズムについて語ってくれた。世界の人気サーフスポットの話になると、決まって議論されるのが混雑する海でのローカルとビジターの関係性だ。近年、さらなる発展を遂げているゴールドコースト周辺のサーフスポットは、ローカルと世界中から集まるビジターサーファーで常に賑わっている。もはや車を停めることすら精一杯の状況だ。ときには海の中で争いが起きてしまい、ローカルがビジターを追い出すような光景も目にする。そんななか、キャロル兄弟は「僕たちはシェアし、助け合わなければ生きていけない。混雑することは素晴らしいことでもあり、地域民としてウェルカムな体制でいたい。それこそが、真のローカリズムなのではないか」と語っていた。

同じくレジェンドサーファー、“ラビット”ことウェイン・バーソロミューも印象深かった。彼はゴールドコーストのワールド・サーフィン・リザーヴ(以下WSR:世界サーフィン保護区)認証化に大きく携わり、現在はゴールドコーストの選挙区に出馬するなど政治家としても活動している。サーファーとして、彼のパブリックの場での発言力と行政とのリンクはとても勉強になった。事実、彼らの活動は海沿いのインフラに大きく貢献していて、シャワーやトイレ、海岸ボードウォーク、ウォーターステーションなどが当たり前のように整っている。年間 を通して公務員ライフガードが海の安全を見守っていることも大きな価値だ。
さらに、オーストラリアでも社会問題となっている海岸侵食に対しては巨大なサンドバイパスでの養浜や、山から運んできた天然石による人工リーフなど、サーファーの意見をもとに自然に優しい手段で対策している。日本で多くの事例がある、サーフポイントとして致命的な「波がなくなる」開発ではないのだ。波あってこそのサーフタウン、このような発展はサーファーだけでなく、地域に住む人々の暮らしも充実させる。そんな地域が一体となって発展を目指す姿が、WSR認証の大きな一手となったようだ。
SFJの拠点がある日本有数のサーフタウン、湘南エリアも、ゴールドコーストの「まちづくり」から学ぶべきことは多いと感じた。それは同時に、SFJのこれからの課題でもある。
次世代の環境活動家、パチャ・ライト
パチャ・ライトはGWCに登壇した唯一の現役女性プロサーファーだった。学者や海洋研究者環境活動家など、名だたる専門家、が自身の研究や活動について発表するカンファレンスにおいても、彼女の輝きは特別だった。
オーストラリアを拠点に世界のコンテストを転戦するプロアスリートでありながら、環境活動家として『Surfrider Foundation』や『Sustainable Surf』など、各環境団体と連携し、環境活動に取り組んできたパチャ。そんな彼女は同じく環境活動家である母アンニャに連れられ、幼少期からたびたび日本に訪れてきた親日家サーファーでもあった。
instagram.com/pachalight/

そんな彼女が今回のシンポジウムで披露したのが、パチャ自身が出演し製作にも携わったフィルム『Woman of the sea』だった。舞台はなんと日本の千葉県御宿と、韓国の済州島。映像にはそれ ぞれの海に生きる海女(あま)さんが登場する。そこを訪ねたパチャが、彼女たちと日々を共にしながら仕事や暮らしを学ぶ姿に、ときおりサーフィンの映像がクロスオーバーされた。暮らしや生命を支える海、サーフィンと海女、生きる土地は違えど、自然の恵みを享受しながら強く美しく生きる女性たちの姿を描いた素晴らしい作品だった。
上映後には会場から大きな拍手が贈られ、日本人である我々SFJメンバーも、異国の地で母国やアジアの誇るべき文化を、パチャのような若いサーファーが発信してくれたことに感銘を受けた。

カンファレンスに参加していた SFJディレクター、永原レキの祖父が韓国済州島にルーツを持つこと、同じくSFJアンバサダーの高貫佑麻のホームが御宿だったことから、私たちはいてもたってもいられずスピーチを終えたパチャのもとへと駆け寄った。そして自分たちが日本から来たこと、舞台となった土地に縁があること、なにより大切なメッセージを日本人以上に強い想いを持って発信してくれたことへの感謝と敬意を伝えると、彼女と母アンニャは、カンファレンスに僕たち日本人が参加していることを心から喜び歓迎してくれた。
サーフィンを通して多くを学び、与えてくれた母なる海に感謝し、自然を大切に想い行動すること。日本人が代々受け継いできた、自然を活かして生きる智慧や、その暮らし方を学び、後世へと伝えていくこと。僕たちはSFJのメンバーとして、サーファーとして、日本人として、それらを実践し広く深く世に届けていきたい。異国から日本の魅力に気づいてくれて、想いをカタチにしてくれたパチャとの出会いは、本当に貴重な財産となった。
高機能かつ持続可能な、美しき日本の伝統を世界へ
GWCの合間にはサーフライダー・ファウンデーションのグローバル・ミーティングも行なわれた。サーフライダー・ファウンデーションのルーツは1984年、カリフォルニアのサーファーたちが自主的に始めたサーフポイントの水質調査活動。日本国内では1993年から活動を開始、2011年に一般社団法人となった。現在は世界23カ国で活動し、約25万人のメンバーが支える国際環境NGOへと成長している。GWCにはアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、そして僕たち日本が参加した。そんな大規模な国際団体のグローバル・ミーティングにおいて、オリンピック開催国ということもあり日本の存在は注目の的となった。

特に興味を持ってくれたのが、徳島県の阿波藍プロデューサーとして活動する永原レキの「日本伝統工芸」の話。藍のほかにも漆など、日本には古来から天然素材が生活の一部として当たり前のように寄り添っていた。しかも、それらはどれも再生可能な資源であり、高機能な素材であり、美しい文化ばかりなのだ。
SDGs(Sustainable Development Goals)が2015年9月の国連サミットで採択されて以降、プラスチック製品などの大量消費や使い捨ての文化があらためて見直されつつある。新しいライフスタイルを築いていくなかで、自然と寄り添ってきた伝統工芸は、エコという観点でも大切な着眼点となるにちがいない。藍色は2020東京オリンピックの公式エンブレムのコンセプトカラーにもなった色。ジャパンブルーとも呼ばれ、日本文化を象徴する色でもある。
カンファレンスではSFJディレクターである石川拳大のアライアや板子の話も披露され、日本人の海との親和性や、独自の文化に寄り添いながら活動するSFJならではの活動スタイルも強く共感してもらうことができた。これからも各国と連携を取りながら、情報を共有し、よりよい環境づくりを目指したいと思う。
SURF FESTIVAL 2020 分かち合おう。自然を、そして笑顔を

SFJディレクターの石川拳大が毎年恒例のように参加しているバイロンベイ・サーフ・フェスティバル。バイロンベイ在住の日本人シェイパー、SURFERS COUNTRYの倉橋潤さんの協力もあり、2020年はSFJメンバーとして共に渡豪した高貫や永原もサーフエキシビジョンに参加。世界中から著名なフリーサーファーが招待参加するなか、高貫はロングボード部門で特別賞を獲得した。また、日本人が持ち込んだウッドボードや藍染ボードはイベント会場でも注目され、大盛り上がりのイベントとなった。国境も文化の壁も超えて波をシェアし、サーフィンを楽しみ、またひとつオーストラリアの素晴らしいサーフカルチャーを目の当たりにすることができた。
この記事の詳細は、発売中のBlue.最新号に掲載されています。
http://www.blue-mag.com